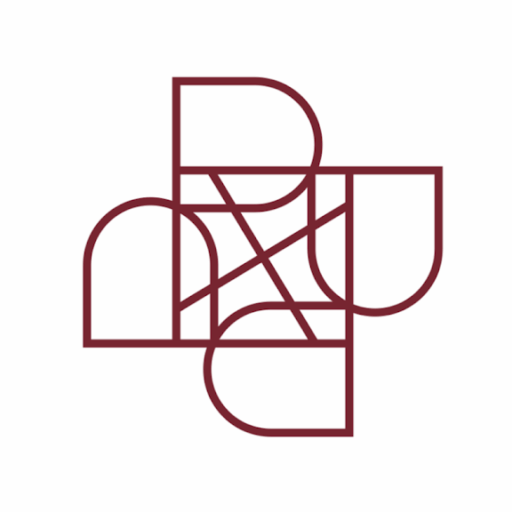Rosetta Contemporary Ensemble
新しい音楽を、新しい形で。
いろんな人と、一緒に。
Photo ©︎ Bibi Nakao 2025
ロゼッタとは?
ロゼッタは、関西地方を拠点とし、音楽表現を中心としたアートコレクティブです。
メンバーは、関西(京都・大阪・兵庫・奈良)、広島、愛知、北海道など、日本各地を拠点にしています。
音楽表現、音楽鑑賞の両面に対し、新たな観点をもたらすことを目標に結成されました。
定期的にゲストコンポーザーを招き、委嘱作品の演奏とともに、公募を行い、世界各国のあらたな作品を世に送り出しています。
2025年にはメンバーで「一般社団法人コロゼッタ」を設立。
ロゼッタとともに(Co-Rosetta)をテーマに
団体としての活動のほか、アウトリーチ、音楽(芸術)コンサルタント、教育活動など
メンバーそれぞれの専門性や興味・関心を反映させながら活動を展開しています。
ロゼッタの主な公演歴
- 「変異するノーテーション Notation:Mutation」京都市立芸術大学移転記念事業 2024年5月
- 「エンカウンター」2023年3月
ロームシアター京都ノースホール(助成:アーツサポート関西) - 「Chamber Concert with Rosetta Contemporary Ensemble」2021年12月
ウェブコンサート、Hong Kong Composers’ Guild主催 - 「2020」 2021年3月
ウェブ展示企画 - 「Reframing」2020年1月
ピッコロシアター室内楽サロン(ピッコロシアター共催企画) - 「フレームを超えて」2019年8月
京都芸術センター Co-program カテゴリーD 採択企画 - 「ロゼッタクラシカル」2019年2月
Flat Flamingo、大阪市(ロゼッタ自主企画) - 「音色の交差点」 2018年8月
遠藤美術館、京都市 (自主企画) - 「未知の空間」ロゼッタ結成公演 2018年2月
京都芸術センター
KAC TRIAL PROJECT / Co-Program 2017 カテゴリーA「共同制作」採択企画
アウトリーチ活動
- 2024年12月 「ミュージアムコンサート」 @ みずのき美術館 (亀岡市)企画・実施
こどもとおとなが一緒に楽しむコンサート企画 (助成:トヨタモビリティ新大阪ASK助成 協力:みずのき美術館)
Rosetta+(大井卓也、日下部任良、柴田高明、橋爪皓佐)出演 - 2023年6月 「四日市市あじさいコンサート」 会場 日永小学校 体育館 主催:日永地区社会福祉協議会
Rosetta+(日下部任良、橋爪皓佐)出演 - 2022年6月 「薔薇の音楽祭」主催・会場:みときや(京都府南丹市)
Rosetta+(日下部任良、橋爪皓佐)出演
活動ハイライト動画
メンバー
アート・ディレクター 橋爪皓佐
アンサンブル・ファシリテーター 日下部任良
コア・メンバー
有馬圭亮(左手ピアノ)
大井卓也(バスバリトン)
日下部任良(サクソフォン)
佐古季暢子(マンドリン)
柴田高明(マンドリン)
橋爪皓佐(ギター、作曲)
アンサンブル・メンバー
上中あさみ(打楽器)
アソシエイト・メンバー
塩地加奈子(ピアノ)
柴田綾子(マンドリン)
西岡美恵子(打楽器)
ゲストコンポーザー
2023-2024年度 塩見允枝子 寺内大輔
2022年度 コーリー・リーダー
2019年度 山根明季子 オースティン・イップ
2017年度 中堀海都 池田萠
2016年度 壺井一歩 川上統
一般社団法人コロゼッタ
ロゼッタと共に(Co-Rosetta)をテーマに、新しい音楽や芸術の形を一般の人々に届けること、社会の中で役立てることを目標として、2025年に設立されました。ロゼッタの運営のほか、アウトリーチ、コンサート企画、ワークショップ、講座、音楽活動コンサルタント、出版など、様々な事業を展開予定です。
奏者紹介
はしづめ こうすけ / Kosuke Hashizume

Photo ©︎ Bibi Nakao 2025
作曲家・クラシックギター奏者として、音と空間、多様なメディアの新たな関係性を探求する音楽家。ベルギー・フランス・イギリス・日本で音楽を学ぶ。
「ロゼッタ」を主宰し、固定概念にとらわれない音楽体験を社会に提示。ロームシアター京都リサーチプログラムリサーチャーや大学非常勤講師も務め、研究活動や次世代の育成にも尽力。一般社団法人コロゼッタ代表理事として、音楽・芸術が日常に溶け込み、誰もが表現・鑑賞を楽しむことができる社会づくりに取り組んでいる。
ありま けいすけ / Keisuke Arima

Photo ©︎ Bibi Nakao 2025
左手のピアニストとして、15年間演奏と研究を続けてきました。生き方のテーマは「旅・音・メディア」。その3つを軸に、国内外で文化活動を展開しています。
主宰する〈ArtVillage〉は、芸術を通じた社会貢献を目指す国際的なプラットフォームで、理念を共有する世界各地の文化グループと連携を深めています。
現在はその理念を地域に根づかせた〈ArtVillage Naganuma〉(北海道)を拠点に、教育や地域づくり、国際交流を通じてアートと社会をつなげる実践を続けています。
関連するイベントは現在ありません。
しばた たかあき / Takaaki Shibata

Photo ©︎ Bibi Nakao 2025
中学校・高校・大学とマンドリンクラブに所属し、その後ドイツにてマンドリンを学ぶ。現在は、マンドリン奏者・指導者として、マンドリン音楽の質を追求すること、また幅広い世代への普及を目指し活動している。室内楽奏者として、「ロゼッタ」での活動だけでなく、毎年4月にリサイタルを開催。ドイツやアメリカなど海外の国際音楽祭やシンポジウムでも演奏。マンドリンオーケストラは、自身の主宰団体の他に、社会人団体、大学公認サークルなど複数の団体を指導するなど、アマチュア愛好家との関わりも深い。特に子ども世代へのマンドリン普及を目指し、「こどもマンドリン工房かえるむ」を設立し、楽器体験を含めた公演を行なっている。
https://www.shibataka.com/
さこ きょうこ / Kyoko Sako

Photo ©︎ Bibi Nakao 2025
広島生まれ。中学校入学と同時にマンドリンと出会う。日本初のマンドリン専攻生としてエリザベト音楽大学・大学院に進学し、その後ドイツのケルン音楽舞踊大学ヴッパータル校を修了。帰国後、マンドリニストとしてマンドリンという楽器の可能性を探究しており、作品の委嘱初演や再演に努めている。また、エリザベト音楽大学の講師や、広島女学院中学校・高等学校マンドリン部などのコーチを務め、後進の指導にあたっている。エリザベト音楽大学ではドイツ語の授業も担当しており、ドイツ留学を希望する学生のサポートも行なっている。
日本マンドリン連盟中四国支部支部長として、中四国地域のマンドリン文化の周知とマンドリン愛好家同士の交流イベントを行うなど、活性化を図っている最中。
広島市被爆体験伝承者でもある。
https://www.sakokyoko.com/
関連するイベントは現在ありません。
くさかべ ただよし / Tadayoshi Kusakabe

Photo ©︎ Bibi Nakao 2025
京都府亀岡市出身のサクソフォン奏者。広島ウインドオーケストラや「ロゼッタ」で活動しながら、日本やアジアの新しい音楽を積極的に紹介しています。愛知県立芸術大学を経てウィーン市立音楽芸術大学大学院を修了し、帰国後も国内外での演奏や指導を行っています。2022年にリリースされたCD『CHANT』はレコード芸術や音楽現代など複数の音楽誌で高く評価されました。現在は京都女子大学や音楽教室で講師をしつつ、ソロやオーケストラでの演奏活動、また京都・森の音楽祭芸術監督として故郷の音楽振興に力を入れています。趣味は珈琲焙煎。好みの焙煎指数は1.20です。
https://www.tadayoshikusakabe.com/
関連するイベントは現在ありません。
おおい たくや / Takuya Oi

Photo ©︎ Bibi Nakao 2025
三重県生まれ。声楽家。小学校の音楽教師がマリー・シェーファーの教育論の実践者だったこともあり、幼いころから自由に音に触れながら育つ。現在は実験音楽の演奏を中心に、他ジャンルの美術家とのコラボレーションなども積極的に行っている。またジャワ・ガムランの演奏グループ、マルガサリの代表を務め、新しいガムラン音楽を追求しているほか、一般財団法人たんぽぽの家のスタッフとして障害のある人とのアートプロジェクトのマネジメントに携わる。アートを通じて人が交わる場をつくり出すことに関心があり、障害のある人や元日雇い労働、過疎地域の子どもとその親など、多様な身体や社会的背景を持つ人との創作ワークショップを行ってきた。
https://x.com/ma97789906
関連するイベントは現在ありません。
かみなかあさみ / Asami KAMINAKA

京都生まれ、京都育ち。高校の吹奏楽部で打楽器と出会う。ピアノが弾けなかったことから、「音楽を続けるにはこの楽器しかない」と、本格的に打ち込むようになる。京都市立芸術大学を卒業後は、フリー奏者として現代曲の初演や異分野アーティストとのコラボレーションに積極的に取り組むと同時に、学校公演を主体とするグループに参加。グループのリーダーが逝去した後に、「ハッピーバースディバンド」を立ち上げた。 同バンドでは、子どもの感性に働きかけるアレンジを心がけたクラシック音楽中心のレパートリーを披露。打楽器とピアノを軸に、さまざまなゲスト奏者を加え、編成を変化させている。また、ダルクローズ・リトミックの要素を取り入れた活動にも力を入れている。 母校の京都芸大では、合奏授業のアドミニストレーター(と呼ばれているが、権力はない)として勤務。学生たちのお母さん役と思い込んで世話を焼いているが、もしかしたら、めんどくさがられているかもしれない。
https://www.duomag.net/